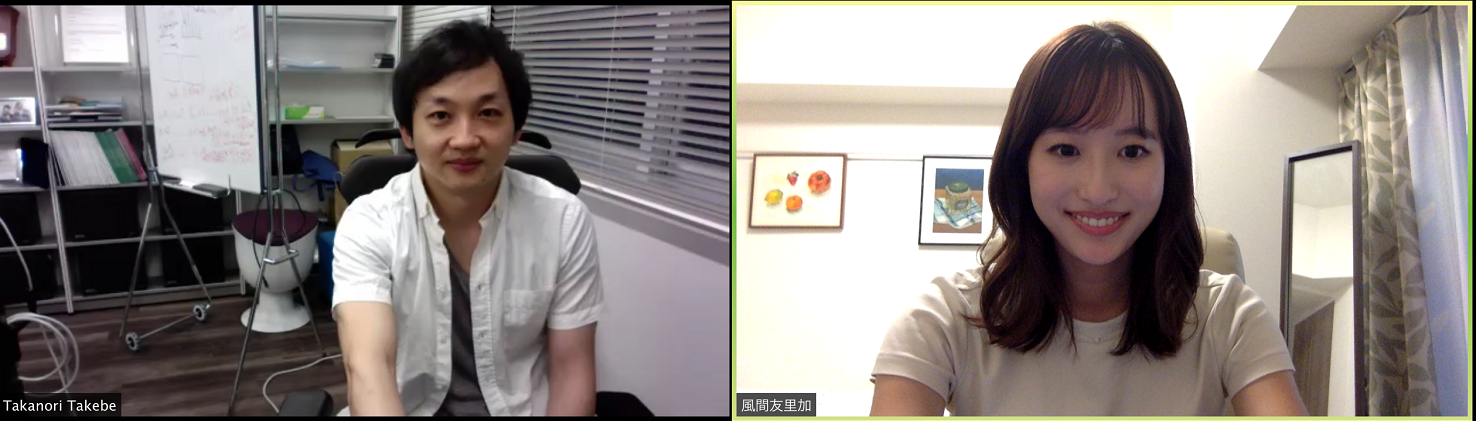
・左:武部貴則先生 右:インタビュアー(風間友里加)
・文責:因間朱里
皆さんがよくご覧くださるのはiPS細胞を使った再生医療のアプローチかと思うのですが、全体としては、いまはどうにもできないような病気や苦しみから人間を解き放てるようなテクノロジーの開発とサイエンスの追求、というのが大きな柱になっています。
各拠点に関してですが、シンシナティ小児病院・東京医科歯科大学・T-CiRAの3箇所の研究内容はオーバーラップしておらず、いわばフェーズをずらしたような形になっています。ざっくり言うと、シンシナティ小児病院では基礎研究、かなりベーシックなプラットフォーム開発をやっています。一方日本では、お金の都合上自由に基礎研究をするのは難しいので、臨床現場への応用を意識した内容を扱っています。東京医科歯科大学では少し応用に寄った研究、T-CiRAではさらに応用につながる研究をそれぞれ行っている状況です。T-CiRAは面白い仕組みをとっており、チームの約9割が武田薬品の社員です。企業の方が大学に来て研究することは普通かと思いますが、僕が大学から出て行って企業の方を指揮しながら研究するのは比較的珍しい仕組みではないでしょうか。
横浜市立大学ではまた全然違って、Street Medicalを扱っています。
アイデアが生まれてくる典型的なタイミングというのは特にありません。Ideationしている瞬間自体が楽しいので常に何かしら考えてはいるのですが、自分の研究領域からほどよく離れた研究を見ている時だったり、全く関係のない領域の人たちと自分たちの研究について議論する時だったりは、アイデアが生まれやすいタイミングかもしれないです。
そうなんです。人生の中で普通は出会わないような人、普通は考えないような物事の中にこそ、何かヒントがあるのではないかと思います。
最初の頃はややひん曲がった性格だったのかもしれないです(笑)。「思い描いていた典型的な医学生のキャリアパスとは違う独自路線をやりたい」というアンチテーゼ的なものが若干あったのかな、僕は確かに普通とはちょっとずれた領域で仕事や勉強をしていることは多かったかもしれないです。
それに対する恐怖感が少ないとは周囲からよく言われます。なんでだろうと思うと、実は兄がミュージシャンをやっていることが影響しているかもしれません。兄のように、自分のやりたいことを絶対やり続ける、そしてその結果に対して言い訳はしたくない、というのが心の底にあるのかもしれません。
正直なところ、研究は絶対やりたかったけれど、いまやりたいことなのかが学生の当時は分からなかったんです。新しい治療法の確立ないしはそれに近いことを目指して仕事がしたいと思っていたのは事実で、その実現方法として研究も選択肢のひとつではありました。でも、もともとは研究がやりたいと思うどころか、むしろ研究者ってなんとなく “イケてない” イメージだったので、その仲間入りはちょっと…なんて思ってたんですよ、実は。
そんなある時、初期研修先探しのための病院見学に行った帰りの電車内である先生に偶然お会いして、「研究もやってるらしいね」と話を振られたんです。で、「研究者というのは希少価値の高い仕事だから、研究続けてみない?できる限りの支援はするから」と言われて。でも、当時は初期研修を本当にやるつもりでしたし、大学院への進学を勧められていると思ったので、その話は一度断りました。だって本当かなぁと思うじゃないですか(笑)。
ところがその後何回か説得いただくうちに、当時は廃止されていた助手というポジションを学内で復活させ、教員として採用する形で研究を続けることを提案されていることが分かりました。そこで少し心が揺らいで、周囲に相談したんです。案の定ほとんどの人には反対されたのですが、唯一肯定してくださった先生がいて。「3年やってみて、研究は自分に向かないと思ったら辞めて初期研修をすればいい。他の学部を一度卒業してから医学部に入り直して医者になる人もいる中で、3年はそれほど大きな遅れではないでしょう」という言葉をいただいて、なるほど確かに、研究はいつかやろうと思っているのだから、だったらいまやろう、と思ったんです。そして最終的にその先生のご提案を受ける形になりました。
医師という職業に大きなリスペクトを持っていた両親には「初期研修はやってからでもいいんじゃない?」と言われ、正直なところかなり悩みました。すぐさま「やってやろう」にはなれなかったんです。
さらに言うと、助手のポジションを作るのもそう簡単ではなかったようでした。(医学部卒業を目前に控えた2011年の)2月頃になって「難しいかもしれない」と言われて。「なんだそれ!」って思いましたけど(笑)、それならば海外で外科研修をしてもともとやりたかった移植医療を目指そうと考え、当時USMLEのstep 1を持っていたので、step 2を取るための勉強を少しずつ始めました。ところがその翌月、当時医学部長だった先生を含め数名の先生のおかげで、入職直前の3月にようやく助手のポジションが確定したんです。研究をやろうと決めてからもなかなか落ち着けなかったので、最終的に研究の道に進めたことは本当にラッキーでした。
いえいえ、すっかり臨床に行く気でした。それどころか、現在でも臨床に戻りたい気持ちはあります。でも、ここまで来て臨床に戻るとなったら、自分たちがこれまでに作ってきた新しい医療を提供する臨床の場を作って戻りたいんです。自分の仕事がどこかの病院の一部門として使われるようになればという夢を持っています。
両方ですかね。いわゆる病院で提供される医療という意味では、iPS細胞や腸呼吸のような新しいテクノロジーを持って行きたいと思いますし、病院の外に出た世の中に対しては、Street Medicalの考え方で世界を変えていくことに少しでも貢献できればいいなと考えています。
そんなに一目置かれていた存在ではなかったと思いますけどね。普通、というか不真面目な学生だったくらいです。ただ、色々変わったのは、3年生で学園祭の委員長をやらされた時でした。やらされたというのも、僕は部活にも委員会にも属さず、あまりにも周りと距離を置きすぎていたので、「何もしていないのはさすがにどうかと思う、だからいちばん面倒そうな仕事をいちばん暇そうなお前に」ってことで押し付けられたんです(笑)。当時は軟骨に関する研究をしていたのですがそれは夜の時間を使い、日中を学園祭の準備にあてました。
あの学園祭は思い出深くて…実は、横市史上最多集客数を記録したんです。土日2日間の学園祭で、土曜日には当時社会問題になっていた妊産婦さんの救急搬送拒否(当時、妊婦たらい回しとメディアで取り上げられ議論をよんでいた)に関する企画を打ったことでマスコミにいくつか取り上げていただいたことで、そこにお客さんがそれなりに集まってくれました。でも、最大の要因は日曜日の芸人さんを呼ぶ枠でした。AKB48の当時のメインメンバー3名と、くわばたおはらさん、さらに小島よしおさんというお三方を、偶然にもキャスティングすることができ、学園祭2カ月前くらいに皆さんスーパーブレイクしちゃったんです。おかげで当日は海に面した横市の狭いキャンパスの全周に人が並ぶくらいお客さんがあふれてしまって、確か万単位になったのかな。そうやって委員長としての業務を通じて周りと関わりを持つようになったり、大きく集客できたことで、多少は周りからの認識が変わったのかな?とは思います。
僕自身はなんでも直接自分の目と耳で確かめたいタイプなのですが、医学部2年生くらいの時、当時東大で教授をしていらした方とお話していた際に「何かに取り組むなら、その領域で世界でいちばんだと思える場所で経験を積みなさい」と言われたのがなんとなく頭に残っていて。例えば留学先としてScrippsを選んだ理由は、Chemistryの領域で世界トップの研究所だと聞いていたので、その研究環境を見てみたかったからなんです。領域としては抗生物質の耐性菌出現メカニズムに関する、一部で大腸菌を扱う以外は完全にChemistryの研究だったので、Cell biologyをやっていた自分にはほぼ何も分かりませんでしたし、加えて当時は英語もちんぷんかんぷんだったので、ものすごい大変でした。
アメリカの方が新しい物事にトライしやすい環境だとは思います。全く違う考えややり方に対してもリスペクトを持つスタンスがあるので、従来と異なることを始める際に、仲間やリソースを確保しやすいです。
それに対して日本は、何かひとつの目標に向けてみんなで一気に走り抜けるのが得意だと思います。ある程度近しいmotivationとmissionを共有できた時、物事を進めるのは日本の方が向いているように感じます。この違いはおそらく多様性を受け入れるカルチャーか否か、というのが影響しているのではないでしょうか。
いい表現ではないかもしれませんが、同じ論文でもアメリカで出していたらあれほど大変ではなかった可能性は否めません。歴史のあるラボやPIのところから出た仕事は、そこの歴史がもつ累積の中で見られるので、やはり通りやすいです。僕自身、最近の論文は通りやすくなっていますしね。当時歴史のないラボから出した論文だったからこそ細かい指摘までたくさん出てきて大変だったというのはあります。
それでも、あの仕事に関しては日本じゃないとできなかったと思っているんです。当時僕はその研究室を3年で辞めることを教授と約束していて、論文を出したのは1年目の時だったのですが、大量に来たコメントを見て、これはあと2年かけても自分の手では完遂させられないかもしれないと思いました。でも、そこで教授が、当時のラボのリソースをすべてその論文のreviseに投入してくれたんです。おかげで、僕自身は4, 5人のスタッフをマネジメントさせてもらいながら、reviseを3年ですべて完結させることができました。これはアメリカでは多分できなくて、あの日本の、あのラボの環境があったからこそ成せたものだと思うので、当時の教授には本当に感謝しています。
多くの研究は、ユニットを徐々に分解して、例えば臓器だったらまず細胞のレベル、それをさらに分子のレベルに分解して、それからメカニズムを考えようという、要素還元的なスタイルで行われます。でも僕らがやったことは、細胞を、1種類だけでなくほかの細胞まで一緒に含めて培養することで、より複雑なモデルを作ろうという考えでした。これは要素を分解して理解しようとする潮流とは真逆なので、そういう意味で最初は「きたない」研究と揶揄されましたし、批判も結構多かったなと思います。
臓器移植に関連して言えば、Columbia大での経験がとても印象に残っています。実は向こうで担当したのは日本人の患者さんだったんです。その方は肝臓移植を受けなければもう助からなかったのですが、なんとか渡米できて幸いにも臓器移植が間に合ったという状況でした。当時は肝性昏睡で意識のない状態で、奥様とお母様がずっと付き添って看病していらっしゃる、そんな時に意外と僕が役立ったんです。医学部の学生である自分は、もちろん外科医としては全く機能しません。でも、命が助かるかどうかギリギリのところで、しかも英語は全くできないという状況で相当精神的にもきつかった奥様とお母様にとっては、ちょっとした翻訳をしたり、困りごとを日本語で質問できたりする相手として僕の存在が活きた。
ここで、ケアの中でできることはまだかなりあるな、と思ったんです。いまの医師・看護師・コメディカル・パラメディカルがやっていることは多分部分的でしかなくて、患者さんをひとりの人間として、あるいはその人が抱えているコミュニティとして見た時に、やらなければいけないはずなのに抜けている部分というのがかなり可視化された感覚がありました。患者さんを相手にすることだけが患者さんのケアなのではなく、そのご家族もhappyな状態になって、患者さんと向き合える状態を創り出すことも患者さんのケアにつながるし、ご家族のhappinessにもなる。だから、そうした領域にまで目を向けられる仕事を作らないと移植医療は成立しないなと強く思いましたし、同じことは生活習慣病や精神疾患などでも言えるのではないかと類推的に考えました。これもひとつ、Street Medicalを考えるきっかけになった経験かと思います。
それはいい質問で、最終的にはcommunity-drivenの設計を仕込んでいくのがベストだと思っています。現在僕たちは、都市開発にコミットして、都市という単位でこれを実現することに最も注力しています。
そもそも僕たちが何をやっているかということですが、多くの取り組みは、病気やHealthあるいはHealth careというコンテクストで行われていると思うんです。でも、それは普通の人間の感覚としては少し違うのではないかと。例えば食事の時も、運動する時も、身体のことを考えているわけではなく、その時点でのパフォーマンスを高めることの方を気にしているはずで。そう考えると、Healthにこだわり続けるのではなくて、より主観的なものとしてのHappinessを扱う軸が必要で、HappyかつHealthyな状態を創り出していかなければいけないと思ったのが、デザイナー・クリエイターが医療において果たせる役割があると考えるに至った大きな理由です。スマホのゲームをきっかけによく外出するようになって認知症が改善したケースがありましたけれど、そうやってHappyを高める結果としてWell-beingになるような仕掛けを作ることで、これまで目を向けてこられなかった領域に楔を打ち込んでいきたいと思っています。それを、まずは個人レベルで提供してきたのですが、現在ではコミュニティのレベルに少しずつ上がってきたので、都市のような大きいスケールで実装するプロジェクトを手掛けている、というのがいまの状況です。
現時点で具体的に言えるのは、横浜・関内駅周辺という環境の中で、様々なステークホルダーすべてが同じvalueを共有して進めるようになるための、グランドデザインを設計している段階だということです。いまはまだ話せることが少ないのですが、来年あたりには大きく公開できる部分があるかなと思います。
教育学者・グラフィックデザイナー・プロダクトデザイナー・ウェブデザイナー・コピーライターといった人たちが常勤でいて、加えてアドバイザリーボードがいます。
そして、Street Medical Schoolというのを主宰しています。先日から第3期が始まりましたが、参加者は日本中から集まっています。内訳としては半分くらいが医療系の大学生・社会人、あるいは製薬会社の方で、残りの半分くらいがクリエイティブ系の専門の方。ここで新たなものを大きく作っていく取り組みをしています。
そもそも僕自身も病院が嫌いで、お医者さんと会話するのも好きではないんです。そのメンタリティーは父親と共通しているのだと思いますが、それでも父親は比較的改善してきているように感じます。でも、母親はもっと医者嫌いなんですよ。健康診断ですら受けたくない、注射嫌い、お医者さんと話すのも怖い、という状態なので、多分婦人科健診を勧めたらますます嫌がるでしょうね(笑)。
ただ、多くの人は同じように思うのが事実でしょうし、そこは大きな課題ですよね。僕らみたいに医療をよく知っている人からしたら健診は受けてほしいなと思いますけど、そうでない人からしたら、身体を触られたり医者に診られたりするのはすごく嫌な経験だろうし。医療を受ける側が嫌なことに向き合える状況を作れるかも大事ですし、それに加えて、これまで同様に医者は待っているだけで患者さんが来る、というのではダメなフェーズに入ってきていて。だから、医療を提供する側も受ける側も課題を解決していかないと、僕自身や僕の両親の抵抗感は解除されていかないと思うので、こうした活動は様々な方々を巻き込んでもっと横に広がっていく必要はあるのかなと思います。
僕は大した人間ではないので僕の言うことを聞くのがいいかは別問題ですが、「思ったより怖がらなくても大丈夫」というのは、特に医学生の方に対してすごく強く言いたいなと思います。医学部を卒業していらっしゃるということは、社会的に見て本当に色々な可能性をある意味ボトムラインで確保できている、要はお医者さんになれるという状況が、あらゆるものに対しての保険みたいなものですよね。仮にどんなチョイスをしたとしても、普通だったら音楽家になったり、いきなりスタートアップを創業したりというのは、すごく大変なモチベーションがないとだめだと思うんですけど、医師免許というポテンシャルないしは保険があるがゆえに、あらゆるものに対する挑戦に際しての恐怖を取り除ける環境にあると思うんです。それを有効活用しない手はないと思うので、何も恐れる必要はないんじゃないかなと。だから、人と違うことでも同じことでもいいと思いますが、一歩踏み出してみるといいんじゃないかなと思いますね。
高校3年の部活動ですね。ブラスバンドをやっていました。うちの高校は高2でだいたい引退なので、高3になった時にどうするかすごく悩んだ末、続けることにしたんです。なぜかというと、卒業後音大に進んだくらい音楽的に熱心だった同期がいたのもあるのですが、勉強に打ち込むのは、多くの人はそうやっているんだろうとは分かっていましたが自分としては嫌だなという思いがあったからでした。音楽がすごく好きだったんですよね、だから僕自身も音大に行きたいとは比較的強く思ってたくらい部活動に対してすごく気持ちが向いていたので、高3でも部活を続けて夏の大会に出ることにしました。
ところが、夏の大会に出ようと思っていたのに、指導してくださっていた先生が夏の仕事を入れられてしまうという事態になってしまったんです。本来は毎日朝から晩まで、夏の間ずっと練習に練習を重ねて、それをもって大会に臨んで勝負をするので、先生もそれにずっと付き添ってくださるはずだったのが、仕事が入ってしまったせいで、僕らの最後の夏が不完全燃焼になるリスクを抱えました。そうしたらその先生、なんと仕事を辞めたんです。「仕事をやってこの3年生との機会を失うよりは、仕事を辞めて皆さんと一緒に夏を過ごして本気で大会に臨んだ方が、人生にとっていちばん大事なことをやれる気がする」って、辞めて僕らと夏を過ごしてくださって。
そうして夏の大会に出ました。僕たちは最終的には関東大会出場を目指していたのですが、結果的に、その関東大会を、数百点満点のところを1点差で逃してしまったんです。しかも、男子校というだけでもともと評価が下げられがちなところ、ほとんどの審査員は高得点をつけてくれました。なのに、1人だけすごい低い得点をつけてきた人がいて、そのせいで1点差で関東大会に行けなかった。仕事を辞めてまで一緒に過ごしてくれた、いまでも恩師と思っている先生との夏が、中途半端で不本意な形で終わってしまったんです。それが心残りで……タイムカプセルを埋めた時にも「やり直したい」と言い続けていた記憶があるんですが、あれはできることなら本当にやり直したいです。もしやり直せたら、そして成功していたら音大に行っていたのかなあ。人生変わってしまっていたのかもしれないけれど、やり直したいと思うとその高3ですね。
これから先、様々な技術革新が進む中で、そうした創造性こそが人間の果たせる強みでもありますし、そういうところに興味を持ってくれる人が医療の現場でも増えたらいいなと思います。医学生や医療従事者はどうしても「間違えることを恐れる」というのを叩き込まれますよね。もちろん、間違った医療を提供してしまうわけにはいきませんから、そうあるべき部分も当然ありますし、標準的なアプローチはもちろん重要です。でも、それだけだったら代替できる技術が今後色々と出てくる。じゃあ、医療の視点から、人間として何か世界に貢献できることがあるとすると、そこでCreativityはすごく武器になるし、そういう意味で研究者というのもひとつの選択肢としてとらえてもらえればいいなと思います。